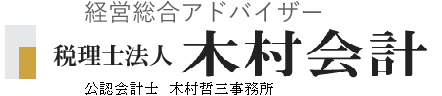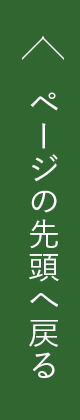もしもの時、家族が困らないために-家族信託と選択肢
テレビで見た認知症のニュース、他人事ではありません
最近、認知症のニュースをご覧になって、不安を感じていらっしゃいませんか?
「もし認知症になったら家族はどうなる?」
「実家の土地や預金、凍結されてしまったら?」
そんな心配を抱えているのは、あなただけではありません。
2022年の報告では認知症患者数は1,000万人を超え、2040年には65歳以上の 5人に1人が認知症になると予測されています。
誰でも起こりうることなのです。
「財産が凍結される」ってどういうこと?
もし認知症になってしまうと、法律上ご本人の判断能力が失われたとみなされます。その後、
- 1. 銀行口座が凍結され、お金が引き出せなくなります
- 2. 不動産の売却ができなくなります
- 3. 介護施設への入居費用も自由に使えなくなります
このような時、民法では「成年後見制度」という仕組みがあります。しかし、これには思わぬ落とし穴があるので注意が必要です!
成年後見制度の現実
- 1. 家庭裁判所の監督下に置かれます
- 2. 後見人の役割は「財産保護」が最優先
- 3. 生活費以外の支出は原則認められません
- 4. ご本人やご家族の希望があっても、自由に財産を使えません
つまり、[財産が事実上、凍結状態]になってしまうのです。
お孫さんの入学祝いを渡したい、自宅をバリアフリーに改修したい、そんな当たり前の願いすら叶わなくなる可能性があります。
「家族信託」という新しい選択肢
家族信託とは、委託者が元気なうちに信頼できる家族に財産の管理をお願いする仕組みです。
例. 家族信託の基本的な流れ
- 1. ご本人(委託者)が、信頼できる子ども(受託者)と信託契約を結びます
- 2. 不動産は子どもの名義に変更されます
- 3. 預貯金も子ども名義の「信託専用口座」で管理されます
- 4. 子どもは財産を管理し、得られる利益を親(受益者)が受け取ります
- 5. 親は受益者として、財産から生じる利益を受け取る権利を持ち続けます
大切な3つポイント
- 1. 名義は子どもに移りますが、利益を受け取るのは親のままです
- 2. 家庭裁判所の監督は不要です
- 3. 家族の判断で柔軟に対応できます
家族信託の4つの安心ポイント
- 1. 【判断能力】があるうちに、ご家族と一緒に将来の計画が立てられます
- 2. 【信頼できる家族】に財産管理を任せられます
- 3. もし認知症になっても財産が凍結されません
- 4. 亡くなった後も契約は継続されます
知っておいていただきたい4つの注意点
- 1. 借入金は信託できません
- 2. 農地は信託できません
- 3. 信頼できる受託者が必要です
- 4. 税金が安くなるわけではありません
上記注意点を鑑みても、「資産が凍結される前に対策を立てられる」これこそが多くの方が家族信託を選ぶ理由です。
今、できることから始めませんか?
家族信託は身体的な不安をきっかけに検討される方がほとんどです。「まだ大丈夫」と思っているうちに、判断能力が低下してしまっては遅いのです。
大切なご家族のためにそして何よりご自身の安心のために、まずはお気軽に木村会計担当者にご相談ください。